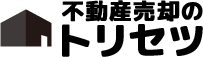令和7年3月4日にマンションの管理及び再生の円滑化等のための措置を講ずる「老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律案」が閣議決定され、区分所有法が改定されることになりました。
いわゆるマンション法と呼ばれるこの法律は不動産投資のオーナーだけでなくマンション管理業者にも大きく影響することになり、改正後の制度を正しく把握することが重要です。
この記事では区分所有法改正の背景と 改正内容について解説しますので、マンションの所有者やこれからマンションを使った不動産投資を検討している人は参考にしてください。
区分所有法とは
区分所有法は民法の特別法という位置づけになっており、正式名称は「建物の区分所有等に関する法律」です。
区分所有建物と呼ばれる賃貸マンションや分譲マンション、団地といった共同住宅に対して適切に管理するための仕組みが規定されており、区分所有者は区分所有法に沿って管理規約や管理計画を作成することになります。
また、マンション管理の委託を受けた管理会社も区分所有法に沿って適正化された修繕積立計画を立案することになり、管理組合と協力して快適な居住環境になるよう維持管理し、問題発生時の解決を試みる管理業務を行います。
このように、区分所有法は区分所有に特化した基本方針となっており、ガイドラインとして活用されています。
なお、よく似た法律にマンション管理適正化法がありますがこの法律は行政法となっており、改正されるのは区分所有法になりますので注意が必要です。
区分所有法改正の背景

区分所有法は時代の変化に伴って課題解決のために改正を繰り返してきました。
2025年になりマンションのストック戸数は700万戸を超え、戸建てと同様に重要な住環境になっていますが、その一方で建物の老朽化と所有者の高齢化が進むことが問題になっています。
しかし現在の法令では議決権を持つ区分所有者の賛成割合でマンション建替えや修繕が決議されることから、所在不明の入居者や相続により代替わりした場合、円滑に決議できないのが現状です。
このような状態で放置していると倒壊の恐れがあるマンションが増加してしまい、さらに不動産の資産価値も低下してしまいます。
そこで国土交通省は適正にマンションを維持管理するために建替えや修繕のルールを緩和する改定案を提出し、2025年に決議によって施行されることになりました。
法律案の概要
改正区分所有法は「マンションの管理の円滑化等」「マンションの再生の円滑化等」「地方公共団体の取組の充実」の3つから構成されています。
この章では国土交通省のHPで公開されているマンションの管理・再生の円滑化等のための改正法案をベースに、詳しく解説します。
参考:マンションの管理・再生の円滑化等のための改正法案を閣議決定~新築から再生までのライフサイクル全体を見通した取組
マンションの管理の円滑化等
「マンションの管理の円滑化等」では、次のような取組みが決定されています。
- 新築時から適切な管理や修繕が行われるよう、分譲事業者が管理計画を作成し、管理組合に引き継ぐ仕組みを導入。
- マンション管理業者が管理組合の管理者を兼ね工事等受発注者となる場合、利益相反の懸念があるため、自己取引等についての区分所有者への事前説明を義務化。
- 修繕等の決議は、集会出席者の多数決によることを可能に。
- 管理不全の専有部分等を裁判所が選任する管理人に管理させる制度を創設。
快適な状態をより長く維持するためには、日常的な点検業務が大切です。
また点検によって修繕が必要となった際に速やかに決議し、工事をすることで安全な住環境を保つことができます。
そのためにはマンション建設時点から管理が適正かつ円滑に推進できる計画が作成されている必要があり、さらにスムーズに決議できるよう議決のルールを緩和することが大事だといえます。
これ以外にも工事内容と発注者について区分所有者に対し事前説明を行ったり、区分所有者が所在不明になっている部屋を管理人が管理できる制度などが盛り込まれています。
マンションの再生の円滑化等
「マンションの再生の円滑化等」では、次のような取組みが決定されています。
- 建物・敷地の一括売却、一棟リノベーション、建物の取壊し等を、建替えと同様に、多数決決議によることを可能とするとともに、これらの決議に対応した事業手続等を整備。
- 隣接地や底地の所有権等について、建替え等の後のマンションの区分所有権に変換することを可能に。
- 耐震性不足等で建替え等をする場合における特定行政庁の許可による高さ制限の特例を創設。
管理をすることでマンションの寿命を伸ばすことはできますが、建造物である以上倒壊のリスクを避けることはできません。
そのため、建替えが必要となった際にスピーディーな判断ができる環境が重要となります。
しかし現行法令では大規模修繕を行う場合は議決権を持つ区分所有者の75%以上、建替えについては80%以上の賛成が必要となり、実現が困難となるケースが多いです。
そこで、修繕や建て替えのルールを割合ではなく多数決で決めることに仕組みを変更する案が盛り込まれることになりました。
さらに現行法令に適用できる耐震工事を行う場合の特例措置も用意されています。
地方公共団体の取組の充実
「地方公共団体の取組の充実」では、次のような取組みが決定されています。
- 外壁剝落等の危険な状態にあるマンションに対する報告徴収、助言指導・勧告、あっせん等を措置。
- 区分所有者の意向把握、合意形成の支援等の取組を行う民間団体の登録制度を創設。
長年住んでいるとマンションが危険な状態になっていても気づかないというケースも多く、第三者からリスクについて報告や助言、勧告する仕組みが重要といえます。
また、修繕や建て替えを進めるためには区分所有者の合意を得ることが重要であり、意向の確認や工事の必要性を説明する民間団体にも協力してもらう必要があります。
このような活動支援団体を設立し、修繕や建て替えを促進させることが目的となっています。
区分所有法改正でマンションの建て替えは進むのか
マンションを建て替えるためには多くの費用を区分所有者が負担しなければなりません。
そのため反対する人も多く、8割以上の区分所有者が賛成することは難しいケースが多いです。
しかし区分所有法が改正し多数決で建て替えが採用されると実現しやすくなり、今後はマンションの建て替えは増加することが予想されます。
まとめ
今回の区分所有法改正によってマンションを新築した時点から円滑に維持管理するための計画が作成され、区分所有者の理解を得ながら必要な修繕をスピーディーに行えるようになります。
また築年数が古く倒壊のリスクがある場合でも大規模修繕や建て替えについて決議されやすくなり、より長く快適な住環境を維持できるようになります。
このことからも築年数の古いマンションを購入する際には今後修繕や建て替えが発生する可能性も考慮する必要があるといえ、居住用だけでなく投資目的でマンションを購入する投資家にとっても押さえておくべきポイントといえます。