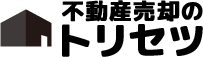土地や建物、マンションといった不動産の所有権を主張するためには「権利証」や「登記識別情報」が必要となり、不動産売却の際に準備しておくべき必要書類の一つです。
そのため所有者は大切に保管しなければなりませんが、相続などによって不動産を取得した場合は権利書や登記識別情報通知書が紛失しているケースもあり、このような場合に備えて対処法も調べておくことをおすすめします。
この記事では権利書と登記識別情報の違いと役割、紛失時の対処法について解説します。
必要になるケースについても紹介しますので、参考にしてください。
不動産の権利書(登記済証)とは? 種類と役割を押さえよう

不動産の権利書は正式名称の「登記済権利証」を略した呼び名であり、登記済証と呼ばれることもあります。
一方、不動産を売却するタイミングで司法書士から「登記識別情報通知書を確認させてください」と言われることもあり、どの書類が分からなくなってしまう売主もいます。
この章では権利書の種類と役割について詳しく解説しますので、所有している不動産を処分する予定のある売主はチェックしてください。
登記済証と登記識別情報の違い
登記済証と登記識別情報はどちらも不動産の所有権を証明するために利用する書面であり、売買や贈与などを原因として法務局に登記するために必要です。
平成17年3月6日までは登記済証が発行され、平成17年以降は登記識別情報通知書が発行されることになりました。
どちらも役割は同じですが登記済証は書類自体に効力があり、登記識別情報通知書は記載されている12桁のパスワードに効力があります。
つまり、所有権を主張するうえで登記済証は原本が必要になるのに対し、登記識別情報通知書は紛失していても12桁のパスワードが判明していれば権利を主張することができることが分かります。
権利書と登記簿の違い
権利書とよく似た書類に登記簿謄本がありますが、権利書の情報に基づいて登記申請を行い、正式な手続きを得て所有権移転されたことを確認できるのが登記簿謄本です。
そのため登記簿謄本でも所有者を確認することはできますが、登記名義人が必ずしも真なる所有者ではない可能性もあるため、注意が必要です。
たとえば相続によって不動産を取得した場合、相続登記しなければ被相続人の情報が登記簿謄本には記載された状態で放置されることになります。
また売買や贈与で取得した場合であっても住所変更や氏名変更が発生した場合、住所変更登記や氏名変更登記をしなければ正しい情報に修正されません。
このような状態で不動産売却しようとするとトラブルが発生し、スムーズに進められなくなってしますので、登記済証もしくは登記識別情報通知書で所有者の確認をすることがポイントだといえます。
参考:登記簿謄本(登記事項証明書)とは?取得方法や見方、必要になるケースについて解説
なお、相続登記については2024年4月1日に義務化されており、相続取得の日から3年以内に登記しなければ10万円以下の過料を科せられることがありますので、不動産を相続取得した際にはなるべく早く登記手続きをすることがおすすめします。
参考:相続登記の義務化
権利書に記載されている情報の具体例
権利証には次のような情報が記載されています。
- 不動産の所在
- 不動産の種別
- 不動産番号
- 受付年月日・受付番号(順位番号)
- 登記の目的
- 登記名義人の情報
不動産番号は登記簿謄本の右上に記載される13桁のナンバーとなっており、登記識別情報通知とは異なる番号です。
登記したからといって所有権移転に必要なパスワードが誰でも閲覧可能になるわけではないため、安心して登記することができます。
ただし登記時点での住所や氏名、抵当権額は公開されてしまいますので、注意が必要です。
不動産売買を行う際には売買時点での登記簿謄本と権利書の情報に相違がないか確認することになり、相違がある場合は正しい情報に基づいてまず不動産登記を行い、その後所有権移転登記の手続きを行うことになります。
権利書はどんなときに必要になるのか
権利書が必要になるケースはある程度決まっており、売買や贈与、相続、抵当権の設定もしくは抹消時です。
ただし全てのケースで必ずしも必要になるわけではなく、例外的に不要となることもあります。
この章では権利書が必要になるケースを紹介します。
不動産売買や贈与、相続時に必要
不動産や売買、贈与、相続といった所有権移転が必要になる場合、登記官は原因発生時点での所有者を把握しなければなりません。
そのため権利書の提出が必要となり、登記簿謄本と内容を突合したうえで手続きを進めることになります。
ただし相続の場合は所有者が死亡していることから所有権移転の意思確認をすることができないため、エラーがなければ不要となるケースもあります。
相続時に権利書が必要となる代表的なエラーとして、次のようなケースがあります。
- 被相続人の住民票に記載された住所と登記簿謄本に記載された住所が異なる
- 被相続人の死亡から5年を経過している
抵当権の設定・抹消など金融機関とのやりとりに必要
住宅ローンを組んでいる不動産を売却する場合は抵当権を抹消する手続きが必要となり、登記申請書に添付しなければなりません。
抵当権は不動産を新しく取得する人にとって所有権を侵害する可能性がある権利であることから、必ず抹消する必要があります。
このことからも速やかに抹消手続きを進められるよう、早めに準備しておくことが大切です。
権利書を紛失したらどうなる?
登記済証や登記識別情報通知書は不動産の所有権移転を行う際に必要となる重要な書類ですが、紛失してしまっていることも少なくありません。
特に築年数の古い実家などを相続した場合、相続時点で権利証がないというケースも多いです。
このようなケースでも慌てることなく対処できるよう、紛失時の対処方法を知っておくことがポイントです。
この章では権利書を紛失した場合にやっておくべきポイントを紹介します。
権利書の再発行はできない
登記済証や登記識別情報通知書は一度しか発行されることはなく、再発行できませんので注意が必要です。
なぜならこれらの書類は所有権に影響を及ぼす可能性が高く、悪用されると所有権が侵害されることもあり得るからです。
このようなトラブルを防止するためにも、権利書の再発行はできないことになっています。
権利書を紛失しても権利には影響しない
権利書は紛失しても所有権を失うわけではなく、映画のように誰かに権利書を盗まれてもただちに不動産を乗っ取られることもありません。
所有権移転登記は登記済証の原本もしくは登記識別情報通知だけで手続きすることはできず、印鑑証明書や本人確認書類、実印なども必要になります。
そのため権利証を紛失していることが判明しても、慌てることなく司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。
権利書を紛失した際の対応方法
権利書を紛失しても正しく対応することで所有権移転登記することができ、スムーズに不動産売買を進められるようになります。
代表的な方法として「不正登記防止申出と登記識別情報の失効申出」と「事前通知制度もしくは本人確認制度の利用」がありますので、それぞれの方法について理解しておくことがポイントです。
不正登記防止申出と登記識別情報の失効申出をする
法務局に不正登記防止申出や登記識別情報の執行申出をすることで、紛失した権利書を取得した第三者が悪用しないようにすることができます。
不正登記防止申出は申請から3ヶ月以内に不正な登記が発生した際に防止することができ、3ヶ月ごとに申請する必要があります。
一方、登記識別情報の失効申出は不正な取引の可能性に関係なく登記を停止することが可能です。
第三者の悪用を防ぐという効果は同じですが必要書類や工数が異なりますので、どちらが良いか専門家に相談して判断することが重要です。
事前通知制度を利用する
事前通知制度は登記が発生した時点で法務局から登記名義人に通達し、登記申請が真実であれば登記手続きを進めるという制度です。
法務局から登記名義人に書類が郵送され、返送して審査完了まで数週間かかりますが、費用の発生はなく不動産登記をすることができます。
ただし審査完了まで登記することができなくなりますので、買主が住宅ローンを組み抵当権設定登記が必要となる不動産取引の場合には注意が必要です。
本人確認制度を利用する
本人確認制度は司法書士などの資格者代理人が申請者と登記名義人が同一人物であることを確認したうえで登記をする制度のことで、身分証明書などの提示によって本人確認を行います。
前述した事前通知制度は登記申請を実施した後に必要書類が郵送されますが、本人確認制度は司法書士と事前面談することで登記に必要な情報を提示することができます。
そのためなるべく早く不動産登記を完了させたいのであれば、本人確認制度がおすすめです。
ただし、司法書士の事前面談や本人確認に対して追加費用が発生してしまうことはデメリットといえます。
まとめ
不動産売却や相続、贈与といった場面で登記済証や登記識別情報通知書が必要になるため、所有者は紛失しないよう適切に保管しておかなければなりません。
なぜなら権利書は紛失してしまうと再発行することができず、事前通知制度や本人確認制度を利用して登記手続きを進めなければならないからです。
こうした制度は時間や費用がかかってしまいますので、所有権移転をスムーズに進めるためにも権利書の有無は重要なポイントといえます。